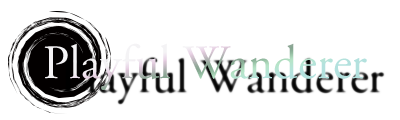悪徳の栄え、美徳の不幸などの方が映像にしやすい気がするが、この作品をどう映像化するか興味はあった。
サドと言えばまあ悪趣味ではあるが、どことなく哲学的、反面教師的、退廃の美学的なものが垣間見得る作品群だが、この作品はあまり信念が見えず、つまりどう受け取って表現したのかな?と。
原作はサドがバスティーユ牢獄投獄中に書いた未完の小説で、全体のプロットはあったらしいが小説として残っているのは序章部分のみ。
18世紀のフランスを念頭に、ドイツ山奥にある古城シリング城という、隔絶した場所でひそやかに狂宴が繰り広げられる。
これをパゾリーニは第二次世界大戦末期のイタリア北部の亡命政権のメンバーの話とすり替え、ネオファシスト運動への批判や、右派や資本主義に対する政治的風刺をこめたものと言われている。
原題の「Salò」とは、ヒトラーに乗せられてムッソリーニがイタリア社会共和国を樹立し、首都であると主張した都市らしい。
一見「ソドム」を現地読みしたものが「Salo」なのかと思ってしまいそうだが、ソドムは「Sodome」であった。この題名がそもそも挑発的だったのだ。
悪徳にまみれた育ち方をした3人のオバチャンの体験談を柱に、大統領・大司教・最高判事・公爵の四人の権力者が模倣しながら興奮するといったストーリー展開。
しかし、権力者の男性共よりも、女衒のようなオバチャンたちの方が、はるかにあくどさが強い。
あと、生贄となった少年少女と同年代の、警備隊の少年らの無関心さ、冷酷さが怖い。
しかし、想像していたほどの衝撃はなく、オバチャンのえげつない物語にピアノの生演奏がついたり、なごやかな食事風景のただ中で、その部分だけやたらリアルな人形を引っ張り出してきて手ほどき教室が始まったり、参加者全裸で花一輪の結婚式(さわり放題)など、どこかナンセンスでコミカルな感じも受ける。原作の方が頽廃色は濃いと感じた。
「地獄の門」の章から「変態地獄」にかけて、
ぼかしもないヘア丸出し、男性器も丸出しの素っ裸も、見慣れると卑猥さも感じず普通の感覚になるもんだな。
「糞尿地獄」は文字通りひたすら排泄物愛の話が続き、そっちの興味がないせいもあるが、そろそろ退屈してきた。
ところへ、、、「血の地獄」の章へ突入。
アコーディオンに持ち替えた、ピアノのオバチャンの寸劇が、超シュールなんですが( ̄▽ ̄;)
気侭に貪り、犯し、殺す権力者の姿が醜いのは当然としても、後半囚われている者同士がお互いを密告し合い、陥れていくさまはより醜い。
ここから終盤に向かっての怒涛の饗宴はもう最悪にきつい。
異状性欲→汚物→、、ときたら、お決まりの悪徳コースは殺人に行き着くわけで、他人の命の軽さとでもいったとこが際立ちます。
ためらいもなく、まるでゲームのような軽さで引き金を引く。
高笑いしながら、非情な快楽のための拷問殺人の話を楽しい話でもするように語るおばちゃん。
それを実行に移すために被害者たちは裏庭に引き出され、あとに一人残された伴奏をしていたおばちゃんは、退屈そうにあくびひとつして窓から身を投げる。
ぼかしがないバージョンを観ていたせいもあるが、拷問場面の描写がものすごいリアルで直視に堪えがたいものがある。
それを楽しげに、双眼鏡で覗く側と直接手を下す側が入れ替わりながら、双眼鏡越しの映像で描かれている。
そして狂気ばしった錯乱状態、もはややられているのは犠牲者なのか警備隊の少年なのかわからない有様もあり、警備隊の少年たち自体が楽しげに拷問の執行となり、、、、カオスの極致で終わる。
最近理不尽にまみれても生き抜く強さと、素晴らしさを感じる漫画や映画や小説ばかりだったのと正反対だ。
AVのように欲情を掻き立てるという風ではなく、かといって映像美を追求したアート的な作品というには汚辱にまみれている。
なんとなく中途半端で間延びした感もあるが、R18では括れないインモラルな映像のせいもあってか、世界各国で上映禁止になったとか。
おそらく政治色の暗喩が強いと受け取られた部分もあるんだろうね。
イタリア社会共和国がそもそもナチスの傀儡政権であったことを考えると、その権力者たちは「Salo」という小さな井のなかで自分たちが全知全能のものであるかのように傍若無人に振る舞う蛙といったとこか。
と、なると、それを高笑いでそそのかす語り手のおばちゃんが実は黒幕のナチ?
無関心に何も考えず権力者にこびへつらう若者の姿は、腐敗した政権の象徴であろうか。その圧政の下でなすすべもなく膝を折って苦渋を舐め、ただ神に祈る民衆。。。。
あくまでも私の私見なので、本当は違うかもしれません。ただ題名が象徴するものから色眼鏡で内容をみるとそうも受け取れるなあと感じたということです。
そして、この映画を撮り終わったすぐ後にネガフィルムの盗難にあい、その後何者かの手により敵意むき出しの殺され方で生涯を終えたパゾリー。時代の闇と思想的な反逆者として受けた烙印の跡をみるのである。
この映画だけの問題ではない。
彼は詩人であり、作家であり、理論家であり、理不尽な社会の批判家であり、少年愛好者でもあった。
映画も社会を告発する表現手法の1つに過ぎなかったのかもしれない。
あまりに厳しく熱く激しく叫び続けることをやめなかった彼の生き方こそがアートと言えるのではなかろうか。
付属の冊子は字が小さすぎるので読みにくいかもしれないが、そんな彼の生き様が紹介されていて非常に興味深かった。