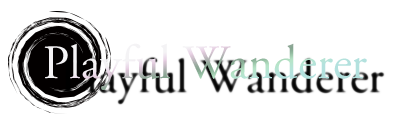前回尾瀬を歩いて体力の衰えが露見したところで、つくばのモンベルに行ってトレッキング向けの服を一式大人買いしてきた。
これで少しやる気を奮い立たせて週末自然散策への目を開かせるのだ!
とりあえずは近場で負担の少なそうな低山の有名どころ、日本百名山のひとつ「筑波山」に足慣らしに行ってみようと。

筑波山には男体山(標高871m)と女体山(標高877m)ふたつの山頂がある猫型(と私は思っている)山である。
登山コースはいくつかあるんだけど、頂上近くまでケーブルカーとロープウェイもあるので、かなり観光化されてて整備も行き届いて初心者向けなんだろなと思った。
そもそも昔地元で何度も登った丹沢大山国定公園の大山だって標高1,252mで、それより低いしコース図に示されてる時間見ても余裕で日帰りできそうだ。
。。。。。なめてましたごめんなさい(--;)
とりあえず今回はいんちき作戦で苦しい登りはケーブルカーでパスすることにした。
まずは縁結びのパワスポとして有名らしい筑波山神社に参拝。
まずは門の手前にある御神橋。
徳川家光公により寄進され、徳川綱吉公により改修されて今に至るという由緒ある太鼓橋です。
普段は通れませんが、春と秋の御座替祭と年越祭の時に限り渡れるようになるそうな。
立派な随神門が迎える。
江戸時代に何度か焼失してるが、現在のは1811年に再建されたものらしい。
御神木の大杉。
筑波山神社の御神体はずばり「筑波山」そのものが「神体山」です。
なのでここも麓からの遥拝所はあるのですが、御朱印はそれぞれの山頂にある本殿でいただくことにしました。
拝殿に本日の無事を祈願してから右奥に進むと、勧請された春日神社・日枝神社があります。
ここには日光東照宮よりも古いと伝えられる三猿の彫り物があります。同じように物語形式で前後のストーリーも彫られていました。
厳島神社も勧請されているので、社務所で技芸上達の札をいただいて納めてきました♪
他にも出世稲荷や愛宕神社、ご神水など見どころはたくさんある神社です。
だから御朱印の種類も多い。。。。
この筑波山神社の裏手にケーブルカー乗り場があります。
眺めはあまりないんだけど、男体山と女体山の間、遠くから見ると猫の額のあたりに到着。
昔ながらのお土産屋や食事処が乱立していて山上なのに観光地化。
とりあえず男体山頂上を目指します。
周辺のこなれた観光地気分とはかけ離れた道ならぬ岩山をよじ登っていきます(^^;)
15分くらいとは言うけれど、足場の悪い山を歩き慣れた人でもないともっとかかります。
傾斜もあるので両手も使いながら足がかりになりそうな岩を判断しながらよじよじ
一応晴れてはいたんだけどかなりガスっていて海の方までは見渡せなかった。
男体山の方はちょっとしたテラス的な見晴らし台に小さな社務所がついてる感じ。
ここで御朱印をいただく。
ここから自然研究路に下っていきました。
やはりそれほど整備が行き届いたという感じでもない細い山道です。
本当はちょっと行った先で小回りして戻れる道があったのだけど、崩落したとかで通行禁止に。
しょうがないのでぐるっとフルに一回りしてくることに。
どんどん下っていくのでいやな予感はしてましたが、やはり最後は下った分、登りで戻ってくることになりましたよ。
かなりの登山客が来ていた割にはこちら側まで来る人は少ないらしく、清々しく静かなブナ森散策を楽しめました。のんびり歩いて1.5hくらいかかったかな。
ロープウェー駅付近まで戻ってきて、女体山側を目指す。
どこのみやげ屋も同じ筑波山名物「がまの油」を売ってるのだけどロープウェー、ケーブルカー駅や麓より安いお手軽価格のもの。値段の違いはよく見れば製造してるところやメーカーが異なるのでそこは好みで。
本当に昔の傷薬としての効能があれば旅のお供として欲しかったんだけど、現在は医薬品の制約とかもあるのでしょう。保湿クリームとでもいった位置づけです。
で、女体山に向かう石段より手前に「紫峰杉」徒歩1分の看板があったので行ってみた。
階段を下ってほど近いところに柵で囲われた大木があったのでこれかな?と思ったらそれはブナの大木
そこから先にさらに下って行ったところに(これ1分以上かかるだろ?)と思ったところで「紫峰杉」ありました!
生で見ないと感動は伝わらないと思うが、今回筑波山散策の中で一番心を動かされた光景がそこにありました!
ただでかいだけじゃない。枝の伸び方や苔の生し方、うごめきそうなその形状なども相まって、ほんと尋常じゃない雰囲気を漂わせていますから~~~。
精霊とか人間ならぬものがきっといる!!
誰もこなければいつまでもず~~~~っと眺めていられそうな気がするパワー溢れる木でした。
そのすぐ向かいには男女川源流があります。
こんな細い筋がやがて大きな流れになるんだから不思議だよね。
女体山方面には名前のついた奇岩がたくさんあります。まずは「セキレイ石」。
鶺鴒(鳥)が石に止まって男女の道を教えたとか。男女の道って、、、そうゆうことかな?
その先に「ガマ石」
ガマ石の口に小石を投げ入れると願いが叶うとかお金持ちになるとか言う言い伝えがあるらしく、私が通りかかったときは遠足っぽい子供たちの集団が一斉に離れたところから石を投げまくっていたため、石の雨が降り注いで危ないので写真だけとって早々に退散しました(--;)
女体山山頂に到着。
こちらの社務所でも御朱印をいただく。
こちらは山頂といっても巨大な岩が積み重なっているようなところで柵もなく結構危険を感じた。
突き出た岩ぎりぎりに立って記念撮影してる人も多数いましたが、完全切り立った崖なので自己責任で。
崖の上だけあって周囲に樹木もなく眺めは開けていました。
ここからつつじが丘に向かってまずは白雲橋コースの奇岩を楽しみながら行く。
こちらがメジャーな登山道だからさっきと違って歩きやすい道に違いないと思ったら大間違い。
やはりごろごろな急傾斜の狭い岩場を足場を確認しながら慎重に進んでいく。
途中鎖場も随所にあり、お子様や老人かよわい女性にはかなり厳しい道であった。
とりあえず「大仏岩」大仏様が鎮座してるようにも見える。
横に石垣のごとくに連なる「屏風岩」
その付近に咲いていたのが多分ツクバトリカブトかな?
がっちりとした「北斗岩」をくぐり
逆からみると、天に向かってそびえたち、ツクヨミ尊を祀る小さな祠がありました。
「裏面大黒」。。。大黒様の後ろ姿??こうなってくるとこじつけにも見えてくるのであるが。
「出船入船」確かに港から出航していく船とこちらに向かってくる船の舳先に見える。結構巨大。
「国割り石」
昔ここに大集合した神々が、それぞれどの国に行くべきか割り振ったと言われ、表面に碁盤の目のようにいくつもの筋が見られる。
「陰陽石」陰と陽の相反するふたつを現した2つの巨石らしいがぴんとは来なかった
「母の胎内くぐり」この文字は各地でよく見ますね。
かなり短い通路しかないのでとりあえず潜り抜けて生まれ変わってみた。
「高天原」急傾斜な高台の上にアマテラス大御神を祀る稲村神社がありました。
しかし筑波山って低いけれど岩山なんですな。普通に歩けるところが少ないから下りだけでも脚にかなり負担がかかる。石垣のようなところも各所にあるが、これは人造なのか自然なのか。。。
「弁慶七戻り」今にも落ちそうな不安定な感じで挟まってる頭上の石に弁慶でさえ潜るのを躊躇したということらしい。
この先分かれ道になっていて、そのまま山を下るか、つつじが丘の方を回って下るおたつ石コース~迎場コースがあるんですが、筑波山で最も眺めがよいコースというおたつ石コースへ向かう。
確かに眺めがいいかなぁと感じたのは、弁慶茶屋跡付近だけだったかな(^^;)
そのまま迎場コースを下る予定だったけど、つつじが丘に巡回バスがあったので、休憩したらもういいかと。
とりあえず見たいもの、寄りたい場所はすべて行ったのであとは特に黙々と下るだけだったので気力が萎えてしまったのだw
そして、、、、4日経ったいまでもバキバキの筋肉痛が治らない。
特に太もも前部の筋肉なんて日常生活で使うことないからなあ。
少しずつ筋力を回復させていかねば劣化は早いとつくづく思い知らされるのであった。