国学・民俗学の研究者としては著名な折口 信夫氏が、普通の小説も書いていた。というところに興味を惹かれて手に取りました。
信仰や風習、伝説等は確かに空想的なものではあるけれど、研究となると、社会背景を捉えながら現実的に解釈してゆくものだから、自ずと感性がちょっと違うと思うんですよね。
この岩波文庫では、「死者の書」と「死者の書 続編」と「口ぶえ」の3作がおさめられています。
岩波書店というと、原文に即した固い文体の印象があるのだけれど、この本は現代語表現に書き下した形になっているようで、読みにくさもありませんでした。
「死者の書」
感覚や記憶といったあいまいな描写ではじまるのだが、出てくる名前や地名から飛鳥〜奈良時代が関わってくることはすぐにわかる。
しかし、この「死者」が一体誰なのか? ここはどこなのか? 最初はわかりそうでわからないやきもきした気分に襲われた。
「伊勢の巫女」「姉御」で一気にピキーーーンときましたねえ(笑
ところどころはいる「擬音」の使い方が非常に美しく、時を超えた想いとあいまって幻想的な雰囲気を醸し出しています。
「死者の書 続編」
実質的な続きではなく、登場人物もがらりと変わります。
静かで美しい文章なのですが、途中でぶつりと中絶しているので(本来まだ草稿の段階だった)、何を本当は表現したかったのか気になる作品。
「口ぶえ」
またちょっと毛色が変わって、現代的な歴史とは離れた内容となる。「私小説」とも言われるようだ。
なんとなく田舎のぼぅ〜〜とした冴えない主人公の日常を、ひたすら淡々と描くので、ちょっと退屈してきた頃にふいにガラっと雰囲気が変わる。
同性からの告白からはじまって、一気に妖しい世界へと全体が塗り替えられて行く。この辺が自伝的と言われるとこなのだろう。
この作品も「前編」でぶつりと終わってしまっているので、なんかもやもや感が残りますね(笑
総括的に言うと、どんどん先が気になって一気に読み進めて行くとか、起承転結がうまくまとまって、わくわくどきどき、、といったたぐいの作品ではないのだけれど、言葉が繊細でゆったりとしているが美しく耽美な流れがある。
噛み締めながら感覚で辿って行くといった感じかな。
どこか澁澤龍彦氏の文章に近い匂いがしました。
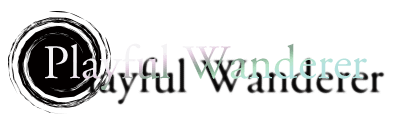




コメント