だいぶ前に買ったはずだが、掃除のついでに本棚の隅で忘れ去られていたのを発見した。
遠藤周作というと、どうもクリスチャンという印象が強く、どこか宗教臭い話になるんじゃないかという偏見もあった。
だが、ここには神の姿はない。
暗い井戸の底で、運命のままに流されて這いずりうごめく人間の姿があるのみだ。
特に劇的に誇張されている訳でもなく、淡々とした様子で、人生に諦観を抱いた人々が登場する。
だからこそなのだろう。いっそう生々しく、飾らない人間の姿が垣間見える気がする。
この本には最初に「あらすじ」がついている。
現代の感覚では理解しにくい状況だからなのかもしれないが、別に文体に難解さはまったくなく、かなりネタバレになってしまうので、飛ばして最後に読んだ方が話の展開が楽しめると思う。
終戦後、誰もが生々しい記憶を持っている頃の話で、ささやかな喜びと当たり前の日常生活の繊細な描写とのギャップが激しい。生活感の漂う写実的な描写力にまず筆力を感じた。
子供の虚栄心、競争心、演技や劣等感なども赤裸々に描かれている。
大人は「子供は無邪気でかわいい」と思いたいところであろうが、誰しもこういう思いや経験はあるのではないか?友達の演技も見抜いては居なかっただろうか?
3歳の幼児でさえ大人の顔色を見て演技することはままあるのだから。
そこからどういう大人に成長していくかは、またそれぞれの人生経験にもよるのだろう。
戦争というのは物質や肉体だけでなく、時には精神まで破壊してしまう恐ろしいものだと思う。
人間が人間らしい思いやりや感情を保っていられる方が不思議な環境。
死と常に隣り合わせの日々の中で、感覚は麻痺していく。
そんな中でも、いや、そんな時だからこそともいえるのか、権力というあいまいなものを巡って醜い競争が繰り広げられる。現代の医療ミステリーとはまた異質なものだ。
良心の呵責に苦しむ人間、その良心というものを探す人間との対比もまた奥行きを出している。
人間という生き物の脆さ、弱さをよく描き出した作品であると思う。
本当に裁かれるべきものは何か。考えさせられるだろう。

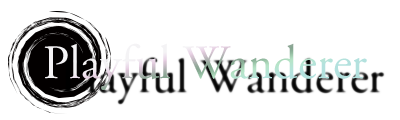


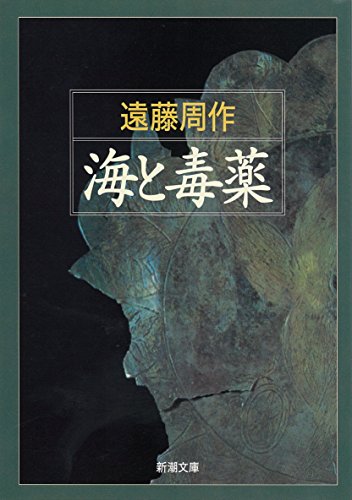

コメント