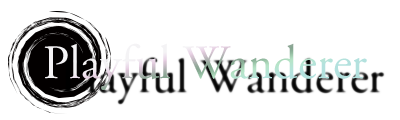12巻~は地球がほぼクトゥルーの異世界に侵略されて、もはや現実世界を完全に離れたサイキックウォーズの様相となってくるので、ここで世界観に入り込めるかどうかで面白さが変わってくる。
とにかく北斗多一郎の涼に対する思いが激しくほとばしり、ちょこちょこと思いの強さが挿入される。
13巻では奇怪なクトゥルーの環境に変えられた世界で、ごく当たり前に生活を送っていたインスマウス人がふと昔人間であったことを思い出してしまうというくだりも面白い。
(ソラリスの海まで出てきたときには小躍りした)
しかし、あくまで理解不能で異物として扱われていたクトゥルーが、ここに及んで妙に分別臭く、人間と近い次元にまで意識が引きずり降ろされてしまったような感じがちと残念。
もちろん特殊な能力をもった者には限られるが、普通に対話が成り立ち言い分が理解できてしまうというのも(最終章ではほぼわかりあい通じ合う気持ちまであるような雰囲気に。。。)、異次元生物との未知との遭遇から国や民族間の地球上のあるあるみたいな身近なものになってしまった。
また、前編では無知な一般人はともかく、安西軍団は最小限の被害で温存されてたものの、後編ではばたばたと死んでいく。
まあ戦争なのだから当然の犠牲とは言えど、あまりにも描写や戦略があっけなく、犬死のように思えるところもあり、なんとなくすっきりしない。
17巻でとうとう18巻では1冊まるごと過去世へ飛び出し、転生のような状態で神代の古代から、キリスト、ブッダ、織田信長、由井 正雪など歴史上の著名人物になりかわって大集合!
まあ、その騒乱の解釈についてはいろいろ思うところもあるけれど、歴史は諸説ありき!だからね。。。
最後には結局「我とは何か」「生命はどこから来るのか」「破滅をもたらすものとは何か」「愛のパワー」といった命題に集結する。
テーマが壮大すぎます。。。。。
終盤に加賀センセが自分のことを「ラプラスの鬼」と言うシーンが頻繁に現れるが、これは「ラプラスの魔」のことであろう。
もしもある瞬間における全ての物質の力学的状態と力を知ることができ、かつもしもそれらのデータを解析できるだけの能力の知性が存在するとすれば、この知性にとっては、不確実なことは何もなくなり、その目には未来も(過去同様に)全て見えているであろう。
ピエール=シモン・ラプラス 『確率の解析的理論』 より
出典: 「ラプラスの悪魔」フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 最終更新 2018年12月3日 (月) 03:34
因果律に基づいて決定する未来、ある種の予知の可能性を記したような内容は神秘思想のようだが 物理学の分野になるらしい。
そして、たぶん直接でてなかったように思うけれど、惑星そのものが大きな生命体という考え方はJ.ラブロックの「ガイア理論」を彷彿とさせる。
また、
我々はどこから来たのか 我々は何者か 我々はどこへ行くのか
ポール・ゴーギャンの絵画作品より
我思う、故に我在り
ルネ・デカルト『方法序説』より
なんのかんの言っても全体的に私が興味をもって見たり読んだりしていたような事柄がぎゅぎゅっと詰まっているので、感性的にはかなり近いものがある!
というか、年を経てみたらより近いとこに来てしまっていたとでもいうべきか。
そして、ラストはやはり壮大なオーケストラが鳴り渡るような圧巻の情景が繰り広げられる。
生と死の大軍勢がせめぎあい、陰と陽のすさまじい交雑が周囲を覆い尽くして視界をふさぐ。
まあ、「結局あれはなんだったの?」「あの話はどこにいったのだろう」と気になるところも多々あるのだが、終わりのようで終わらない「続く」みたいなエピローグなので。。。。実際続編となる「新・魔界水滸伝」も出てるしそこで明らかになる面もあるのだろうか?
とりあえず改めて問題です。10代の頃の自分が果たしてどこまで理解できてたのか(^^;)
それ以降に得た知識と経験で圧倒的に理解が深まったのは間違いないし、当時知るはずのない事柄が多すぎる。
きっとそこは「無知の知」とでもいうもので、わからないことはわからないと認識した上で楽しんでいた面もあるのだろうさ。